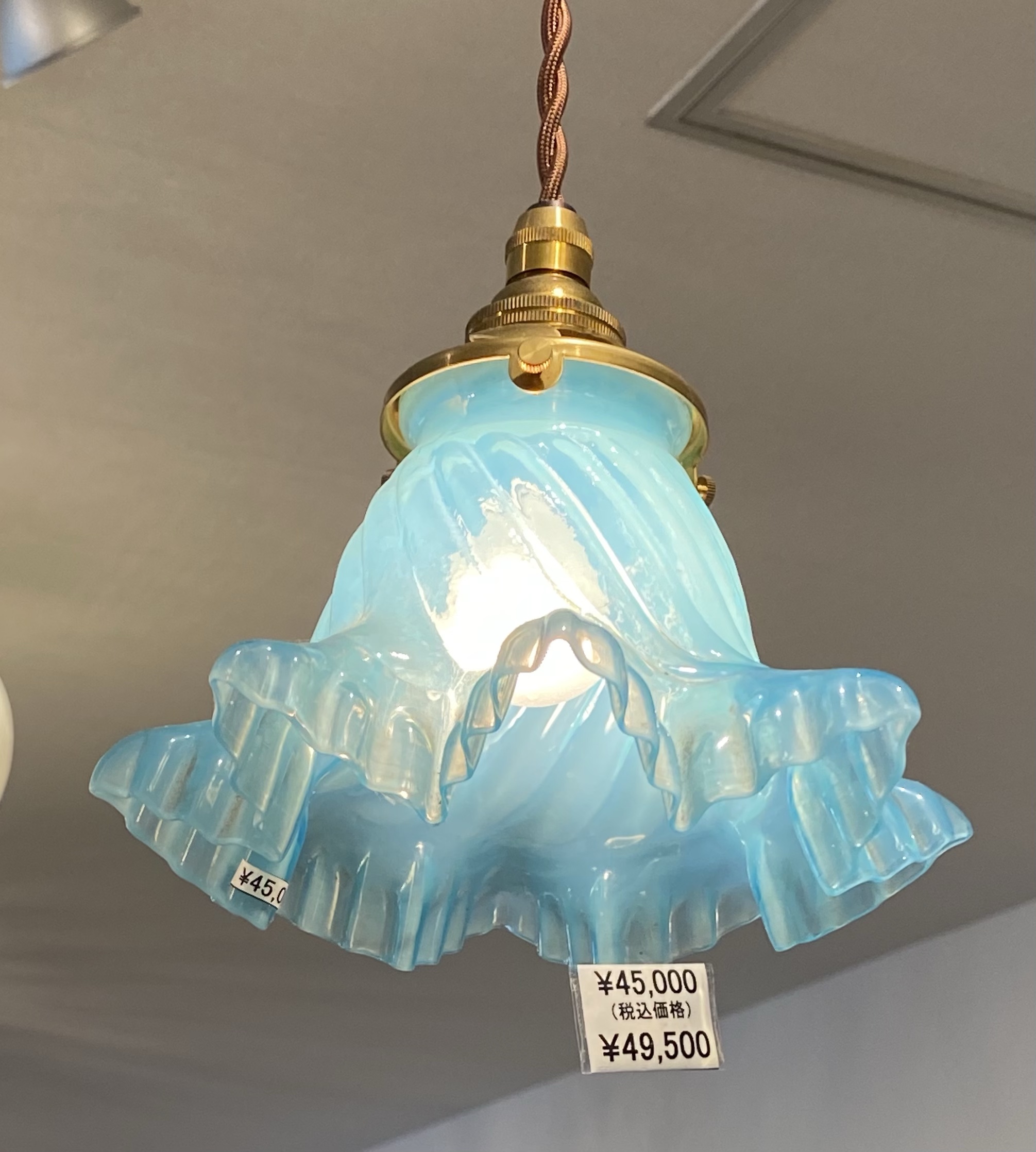私は古民家鑑定士1級を持っています。
でも、そもそも古民家鑑定士とは何をする人の事でしょう?
その事を説明するシリーズを書こうと思います。
まず第一弾「古民家ってどれが古民家?」です♡ ←意味のないハートを付ける55歳
古民家の基準
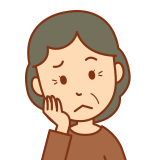
古民家って古かったら古民家なの?
いえいえ、一応基準があるわけです。
ざっくりゆうと、築50年以上経過している木造軸組構法の伝統構法または在来工法の住宅です。(*今後は昭和25年の建築基準法の制定時、すでに建てられていた伝統構法へ修正予定)
ちょっと難しいですか?
もっと噛み砕いていうと
伝統的な様式で造られた「農家」「漁家」「商家」「町家」それに、中級から下級武士の「侍屋敷」の年代の古いもの
という事です。
上級武士の家は、古民家というより城
ですね。
築50年って、そんな武士の時代まで遡らなくても、、、結構つい最近の話。。。。。私にはですよ!!
50年なんて、あなた、この間ではないですか!もう半世紀以上生きているんですよ!私は!←話ズレまくりの図
古民家の種類
一言で「古民家」と言っても、「建築基準法」制定前に建てられた「伝統構法」と、後に建てられている「在来工法」があります。
どうして「建築基準法」で分けられるのでしょうか?
建築基準法が制定されたのが昭和25年。戦後5年です。
戦後の圧倒的な住宅不足の中、資材も人材も足りない中、復興に向けてどんどんと家が建てられた訳です。
「こらこら、待て待て、そんなすぐに壊れてしまうような家を建てるんじゃないぞ!」と、「とりあえず基準を決めましょう」と制定されたのが、「建築基準法」という訳です。
ですが、
伝統構法に比べ小径材が使われ、柱と梁の接合部などに金属が使われるなど、それまでの伝統構法とは違う工法で造られていきました。
(②伝統構法と在来工法へ続く)